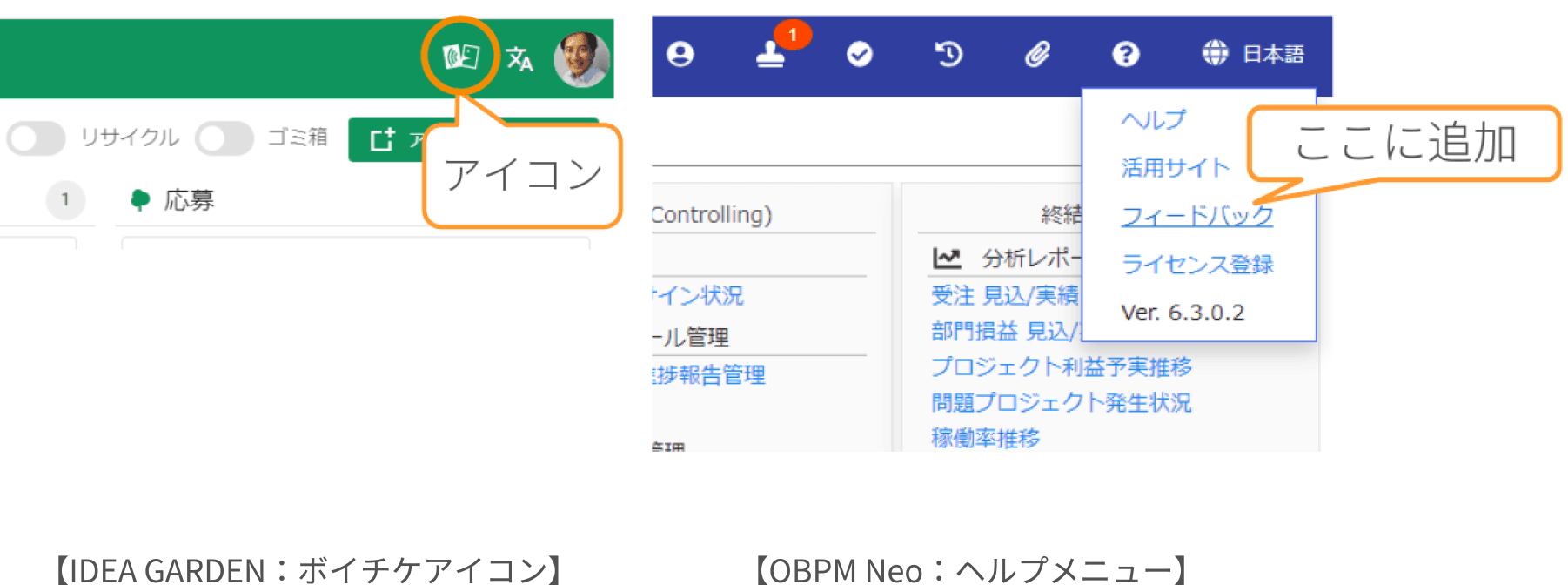導入・運用
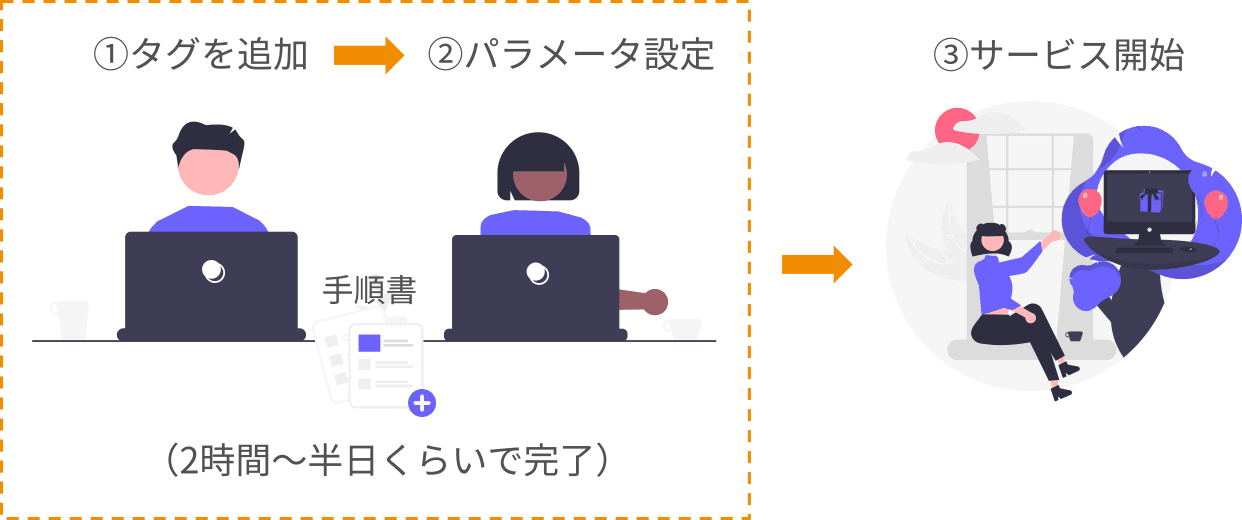
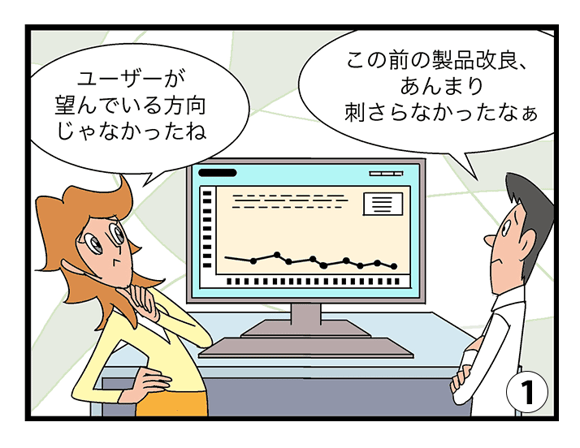
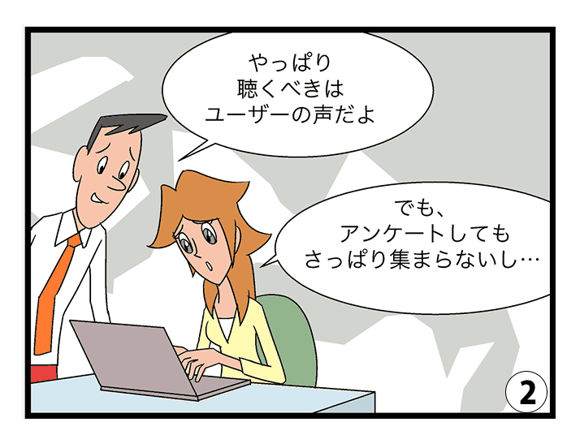
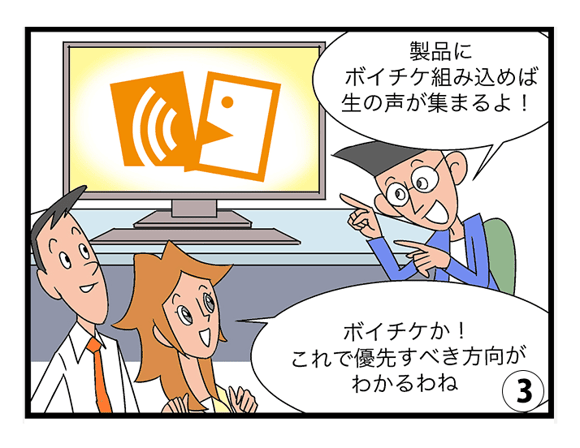
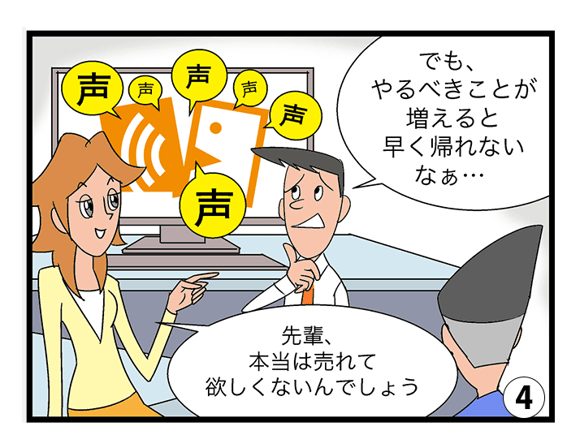
ボイチケタグの設定作業
ボイチケタグの組み込みはとても簡単です。導入手順書がありますので、動作確認も含めて2時間から半日くらいで完了します。
①タグを追加
当社で提供するサンプルタグ(数行のコード)をコピペして自社のサービスや製品のコードに組み込んでください。
②パラメータ設定
ボイチケは、利用者がログインしなくても要望を書き込めます。利用者の所属企業や利用者idなどを自動で受け取るためのパラメータ設定を行ってください。
③サービス開始
後は製品やサービスを提供するだけです。ひっそりとアイコンが表示されるのもいいですが、お客様に「ご要望をフィードバックできるアイコンを追加しました」とアナウンスした方がより早く要望が集まります。
ボイチケの運用
ボイチケは、利用者(エンドユーザー)が製品やサービスを利用している最中に気づいた要望を直接フィードバックでき、双方向コミュニケーションできます。画面遷移図をベースに基本的な運用方法を説明します。

(1)利用者が要望を登録
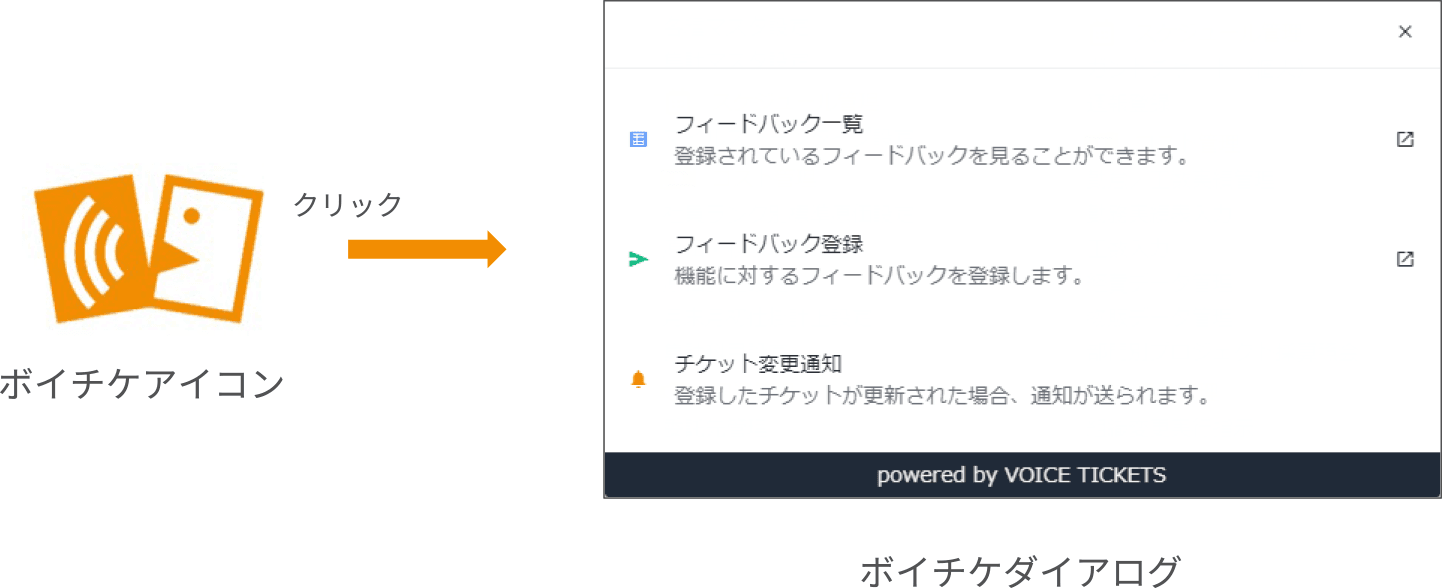
製品・サービス利用者が「ボイチケアイコン」をクリックすると「ボイチケダイアログ」が表示されます。
(2)フィードバック一覧
ダイアログの一番上をクリックすると、チケット(フィードバック)一覧を見ることができます。ボイチケでは、「要望をあげたのになしのつぶて。要望がどう受理されたのかわからない」という不満を防止するため、利用者がチケットの状態を見ることができます。
ただし、事業者は次の4つの「チケット公開設定」により表示コントロールできます。
a.非公開…自分があげたチケットのみ見えます
b.同組織…自社の人たちのチケットが表示されます
c.サービス利用者のみ…同じ製品・サービスを利用している人のみチケットが見えます
d.全公開…当該の製品・サービスを利用していない人であってもチケットが見えます
(3)フィードバック登録
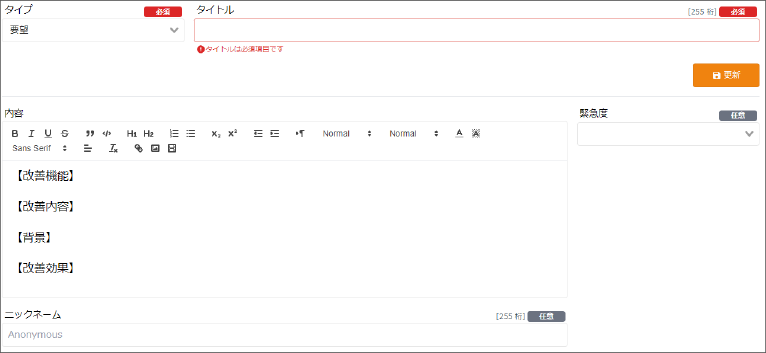
ダイアログの2番目をクリックするとフィードバック登録画面が表示されます。利用者は、ここに要望やクレームを書いて直接思いを伝えることができます。
a.タイプ
「要望」「不満」「障害」「メッセージ」などチケットのタイプを選択します。どのようなタイプを用意するかは事業者が自由に設定できます。
b.タイトルと内容
利用者はタイトルと内容を記述して投稿します。全くフリーに書いてもらってもいいですが、この例のように改善機能~改善効果などの文字を初期セットして、書いてもらう内容をガイドすることもできます。
c.ニックネームや緊急度
投稿者のニックネームや緊急度などを任意で書いてもらったりもできます。
(4)チケット変更通知
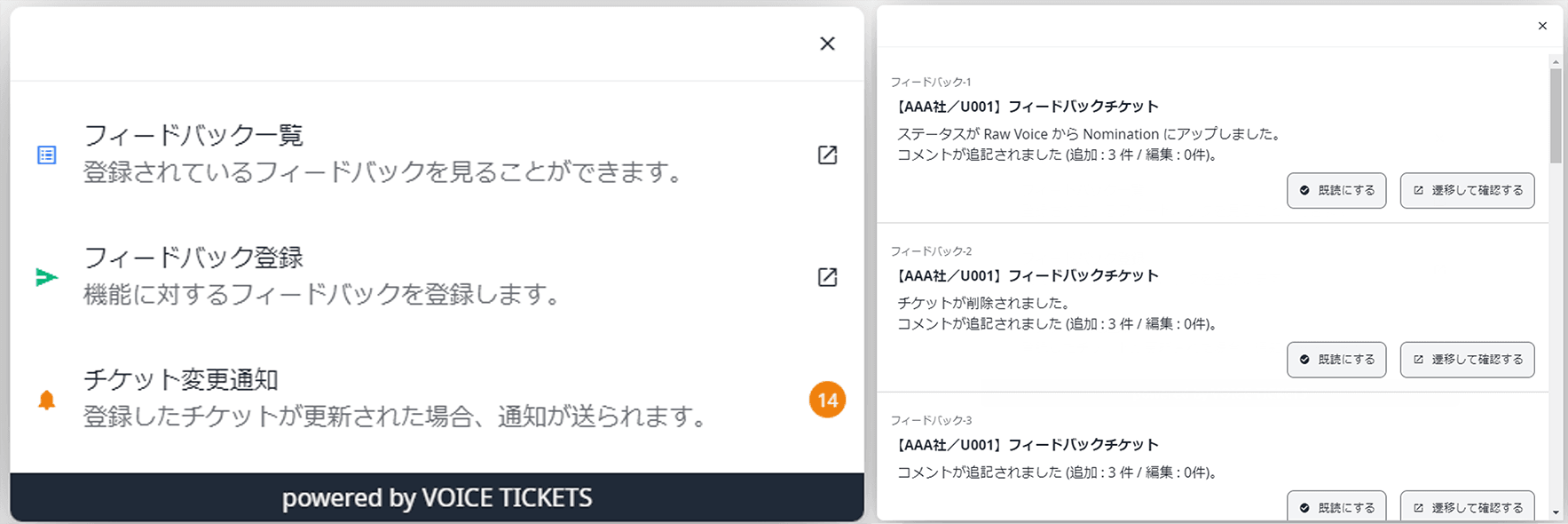
利用者からの声(チケット)を吸いあげるだけでなく、コメントを返して双方向コミュニケーションができます。
利用者は自身の声(投稿したチケット)に対して事業者からリアクションがあると変更通知にて、
- 追記されたコメント数
- ステータスの変更
- チケットの削除
などを確認することができます。
(5)事業者がRaw Voiceをチェック

利用者からの声はRaw Voiceに蓄積されます。事業者は定期的にVoice Board画面でチェックし、次のような感じでRaw Voiceをさばきます。
a.Raw VoiceをVoiceに登録
Voiceに登録=一般に受領したという意味合いで使います。
b.Raw Voiceにコメントを付けてClosedに移動
コメントの例「ご要望ありがとうございます。今後の検討に役立てさせていただきます。」
また、対応が完了Completedしたチケットを定期的にClosedに移す運用も一般的です。
c.Raw VoiceのままDelete
残念ながら他の利用者にとって有益とならないような声の場合は、そのまま削除するケースもあります。
(6)事業者が声(Raw Voice)に対してコメントを返す

カスタマーサクセス成功の鍵は利用者とのコミュニケーションにより顧客満足度を向上することです。
事業者は、チケットに対してコメントを付けて返し、利用者とやり取りすることができます。
(7)事業者がVoiceのステータスを管理
事業者は定期的にVoiceを棚卸して、適切なステータスにします。
ステータスは次のような運用想定になっています。
a.Voice(登録)…要望として認知・登録した
b.Nomination(候補)…改善・対応の候補とした
c.Planned(計画済)…改善・対応を計画した
d.In Plogress(実行中)…改善作業中
e.Completed(完了)…改善・対応済
f.Closed(クローズ)…案件をクローズした
なお、各ステータスは下記画面の設定により非表示にもできます(ここではClosedを非表示)。
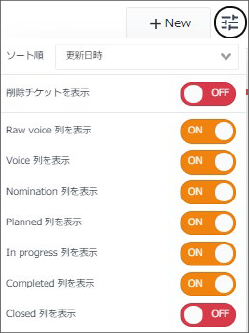
上記の運用で実現できること(まとめ)

①簡単に導入準備ができる
②利用者は簡単に要望をあげられる
③事業者は利用者の声を聴いて対応できる
④利用者と事業者で双方向コミュニケーションが取れる
⑤事業者は蓄積されたチケットを改善に役立てられる
まずはお気軽にご相談ください